1. 科目の特徴
「生命保険と税法」は、日本の税制と生命保険の関わりについてまとめた内容です。業界共通教育制度の中で部分的には登場する内容ですが、扱う範囲が広くそして格段に深くなっています。専門用語が多くテキストを読み進めるのに負担を感じる人も多いでしょう。
2. 試験の難易度
難易度は、平均合格率80.4%(8科目中5番目)と真ん中くらいです。合格率の変動が小さいことから、試験ごとのばらつきは少ないとみられます。ただし、専門用語が多くテキストの分量も多いことから、十分準備することをおすすめします。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 2008 | 81.1% |
| 2009 | 83.3% |
| 2010 | 82.7% |
| 2011 | 74.7% |
| 2012 | 82.0% |
| 2013 | 80.7% |
| 2014 | 86.0% |
| 2015 | 80.6% |
| 2016 | 75.7% |
| 2017 | 77.4% |
| 最高 | 86.0% |
| 最低 | 74.7% |
| 平均 | 80.4% |
3. どんな内容なの?
テキストは7章構成で分量は8科目のなかで最も多くなっています。前半で主な税制について解説し、後半で生命保険商品や会社との関わりについて解説しています。テキストの分量の約半分が6章・7章に割かれています。各章の概要は下記の通りです。
1章 総説
租税はどのような機能をもっているか、また租税の種類および税の用語について理解する。
2章 所得税
所得税における所得の種類および生命保険料控除等の所得控除について理解する。また、所得税額の計算構造を理解して所得税の全体像を把握する。
3章 相続税・贈与税
相続税額・贈与税額の計算方法を理解し、相続税・贈与税の全体像を把握する。
4章 法人税
法人税の性格を理解し、また法人税額の計算方法を把握して、会社利益と所得金額の調整について理解する。
5章 地方税
地方税の体系を理解し、住民税、事業税、固定資産税および不動産取得税の内容についても理解する。また、個人住民税について、所得税との関係および生命保険料控除の計算等を理解する。
6章 生命保険商品と税
個人保険企業保険および財形保険にかかわる税務取扱いについて理解する。
7章 生命保険会社と税
生命保険会社における法人税の特別取扱、事業税の税額計算および職員等関係税務について理解する。
※出典:生命保険協会「生命保険講座 生命保険会計」より各章のポイントを抜粋
4. 頻出単元
下記リンク先のnoteでは、「生命保険と税法」の過去10年分(2013-2022年度)16回の過去問を独自に分析し、頻出単元を割り出しました。独自に算出したカバー率をもとに、メリハリをつけてテキストを進めれば、効率的に学習を進めることができます。適宜ご活用いただければ幸いです。

その他参考
試験まで時間がない方は、テキストより先に過去問から取り掛かることをおすすめします。併せて過去問解説もご活用ください。過去問解説はこちら↓

生命保険講座の攻略ツールとして「過去問のハイライト」を開発しました。新形式の過去問12回分から頻出問題を抽出・再整理した、いわば頻出問題集です。
「過去問のハイライト」はこちら↓


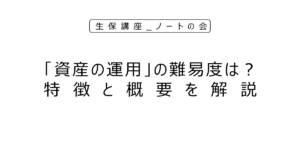
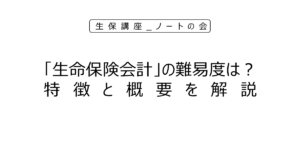
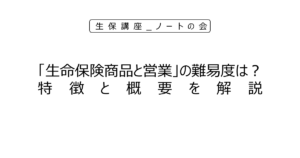
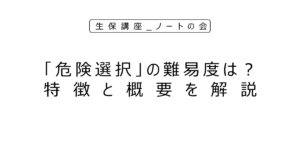
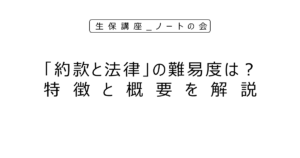
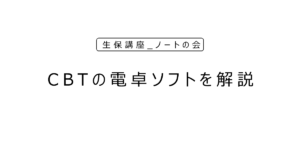
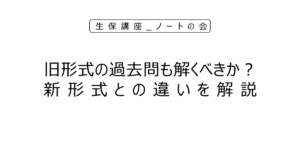
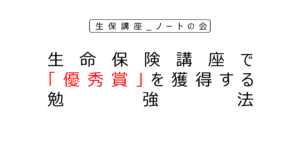
コメント